普通にAppleWatchの最新シリーズを待っていた私に取っては、Apple Watch SEなんて興味のかけらもないのですが、興味のかけらもないのではありますが、少し安すぎるので気になって調べてみました。

2024年の「Apple Watch SE」新着情報まとめ
Apple Watch SEについて調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。
Apple Watch SEに関する新着ニュース
カテゴリ名に関する新着ニュースをまとめています。
Apple公式の割引販売「整備済製品」にApple Watch SEの在庫追加
- Apple Store公式サイトで販売されている「整備済製品」では、iPadやMacBook、Apple Watchなどが最大15%オフの割引価格で提供される。
- 8月17日12時40分時点でApple Watch SEとその他のモデルに在庫追加。
- 売り切れの可能性があるため、実際の在庫を公式サイトで確認することが推奨される。
8月17日の整備済製品の在庫一覧
| 製品名・モデル | ケースとバンド | 価格(税込) |
|---|---|---|
| Apple Watch SE(第2世代, GPSモデル) | 40mmスターライト/スターライト | 31,800円 |
| Apple Watch SE(第2世代, GPSモデル) | 40mmシルバー/ホワイト | 31,800円 |
| Apple Watch SE(第2世代, GPS + Cellularモデル) | 40mmシルバー/ホワイト | 38,800円 |
| Apple Watch Series 8(GPSモデル) | 41mmスターライト/スターライト | 50,800円 |
| … | … | … |
| Apple Watch Series 8(GPS + Cellularモデル) | 45mmグラファイト/ミッドナイト | 95,800円 |
※上記は一部の在庫情報を示しており、完全なリストはApple公式サイトを参照してください。
Apple Watch SEの新製品情報
Apple Watch SEの新製品情報についてまとめています。
直近のApple Watch SEのセール情報
Apple Watch SEの商品で、「これはお得!」と感じたセール情報も残しておきます。購入の決め手となる価格の参考にどうぞ。
Apple Watchのセール情報に関してはこちらの記事でまとめています。

Apple Watch SEの特徴
まず、割と長い記事になってしまったので要点だけ押さえると、Apple Watch SEの特徴はこんな感じです。
Apple Watch SEってこんな感じ
- Apple Watchとしてのコスパは史上最高
- ほぼSeries 6との使い方に違いは出ない
- デザインもほぼ一緒
- Series 6を買うか悩んだら「酸素測りたいか」自問する
- 将来的な拡張性はSeries 6に軍配
- 9割くらいの人はSE買っておけば十分に幸せ
記事の後半で散々書きましたが、新機能である「血中酸素濃度アプリ」と、認可がおりた「心電図アプリ」の時点で、かなり大きくSeries 6に心を奪われます。

ただ、実際に使う場面を想定すると、どう考えてもSEで十分、ってなるんですよね。
Apple Watch Series 3や6と何が違うの?

現在、発売されているモデルは、Series 3、SE、Series 6となります。購入の目安とはしては、以下のような感じで線引きしたらいいと思います。
スペック比較表
まぁ、自分で言うのもなんですが、公式HPにもっとみやすい表があります。
https://www.apple.com/jp/watch/compare/
| スペック項目 | Series 3 | SE | Series 6 |
| ケースサイズ | 38mmまたは42mmケース | 40mmまたは44mmケース | 40mmまたは44mmケース |
| ディスプレイサイズ | 感圧タッチ対応OLED Retinaディスプレイ(第2世代)、1,000ニト | 30パーセント以上大きいディスプレイ10 | 30パーセント以上大きいディスプレイ10 |
| ディスプレイの鮮明さ | – | LTPO OLED Retinaディスプレイ、1,000ニト | LTPO OLED常時表示Retinaディスプレイ、1,000ニト |
| 対応通信 | GPSモデルとGPS + Cellularモデル | GPSモデルとGPS + Cellularモデル | GPSモデルとGPS + Cellularモデル |
| SoC(CPU) | S3(デュアルコアプロセッサ搭載)、W2ワイヤレスチップ | S5 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)、W3ワイヤレスチップ | S6 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)、W3ワイヤレスチップ、U1チップ(超広帯域) |
| Digital Crown | Digital Crown | 触覚的な反応を返すDigital Crown | 触覚的な反応を返すDigital Crown |
| 健康センサー | 光学式心拍センサー | 光学式心拍センサー | 血中酸素濃度センサー、第2世代の光学式心拍センサー |
| ヘルスアラート | 高心拍数と低心拍数の通知 | 高心拍数と低心拍数の通知 | 高心拍数と低心拍数の通知 |
| 緊急時通報 | 緊急SOS3 | 海外における緊急通報4、緊急SOS3、転倒検出 | 海外における緊急通報4、緊急SOS3、転倒検出 |
| 耐水性 | 50メートルの耐水性能1 | 50メートルの耐水性能1 | 50メートルの耐水性能1 |
| 通信規格 | Wi-Fi、Bluetooth 4.2 | LTE、UMTS6、Wi-Fi、Bluetooth 5.0 | LTE、UMTS6、Wi-Fi、Bluetooth 5.0 |
| コンパス | GPS/GNSS、気圧高度計 | GPS/GNSS、コンパス、常時計測の高度計 | GPS/GNSS、コンパス、常時計測の高度計 |
| スピーカー | 内蔵スピーカーとマイク | 音量が50パーセント大きいスピーカー10、内蔵マイク | 音量が50パーセント大きいスピーカー10、内蔵マイク |
| データストレージ | 容量8GB | 容量32GB | 容量32GB |
スペック的には、Series 3はもう検討外か
個人的な感想ですけど、Series 3に関しては、だいぶ見劣りするスペックとなりました。誰かからプレゼントしてもらうなら嬉しいですが、自分でお金を払うような価値はなくなってきたように思います。
SEとSeries 6を比較解説する
というわけで、早々にSeries 3は比較対象から除外しました。旧モデルの情報が知りたい時は、既に過去の遺産と化したSeries 比較記事をご覧ください。

サイズ感はSEとSeries 6は同規格

これ、結構大事だと思うのですが、Series 6 とSEのサイズが一緒です。理論上は、バンドや保護シールなどを共有できます。
素材の選択は自由が効かない
SEは素材が「再生アルミニウム」しか選べませんが、コスパに還元されているので大いにありだと思います。
Series 6の豊富な仕上げ加工
- アルミニウムケース(Nikeモデルあり)
- ステンレススチールケース(Cellulerのみ、Hemesモデルあり)
- チタニウムケース(Cellulerのみ)
スペックに差はあれど実用性に大差なし
SEとSeries 6では搭載チップに差がつけられましたが、全く問題はないと私は評価しました。
SoC(CPUチップ)はSeries5相応
Series 6 はやや進化したS6 SiPを搭載していますが、SEは前作のSeries5と同じS5 SiPを搭載することになりました。
スペック的には遜色ない、までは言えないかもしれませんが、個人的にはチップの優劣は決定要因としては弱いかな、と思います。
今回は、できることがCPUスペックを要求することよりも、ヘルスモニタリング用の特殊センサーを搭載しているか否か、の方が大きいかと。Apple Watchなどのスマートウォッチを利用したいと考えている方は、きっと健康維持にも興味があるはず。

U1チップ(超広帯域)だけは気になるところ
しれっと追加されているU1チップですが、実はiPhone11から搭載されるようになりました。
アップルが独自に手がけたU1は、超広帯域無線(UWB)と呼ばれる無線技術を利用するためのチップだ。アップルはUWBについて、「リヴィングルームほどの空間で機能するGPS」と表現している。UWB技術はWi-Fiに似ているが、基本的に干渉が少ない周波数帯を利用することから、より高いパフォーマンスが期待できる。
https://wired.jp/2020/06/21/u1-chip-future-of-apple-6/
簡単に言えば、位置情報を発信・受信(通信)する無線機能です。何がすごいのかと言えばその精度がすごいということになります。
現段階で「これがすごい!」と説明できるような機能はないのですが、今後発売されるであろう、忘れ物防止タグ(Air Tags?)にこの技術が取りれられることで、実感できるレベルで「すごい!」となるのではないでしょうか。
Apple WatchはU1チップがあった方がいいかも
まだ、実機レベルで「U1チップ、すげぇ」となった実例がないので妄想(イマジネーション)を駆使してApple Watch がU1対応したメリットを考えてみます。
個人認証がApple Watchでできるようになると
まず、Apple Watchは個人認証(セキュリティ)としても重要な役割を持たせられると思います。現在も、MacのパスワードはApple Watchで解除できます。これは便利です。Apple Watchは様々なセンサーを搭載しています。現在のところ、Apple Watchのセキュリティは、パスコードかiPhoneに依存しています。iPhoneは顔認証などで、一般的なパスコードよりは複雑なセキュリティ対策が可能です。
でも、いくら身につけている間はロックパスできるからと言って、ロックを解除するのは少し手間だし、パスコードだけだと心配だし。
Apple Watchで生体(静脈)認証
指紋認証くらいはApple Watchでも搭載可能だと思いますが、それよりも、せっかく血中酸素飽和度を調べられるようになったのだから、静脈認証などが導入されればいいと思います。
光を届けて、読み取ります。 まず緑色と赤色のLEDと赤外線LEDが手首の血管を照射して、その反射光の量をフォトダイオードが読み取ります。そして、先進的なアルゴリズムが体に取り込まれた酸素のレベルを示す血液の色を計算します。
ちなみに、みんなサチュレーションのことを知っているていで書き始めてしまいましたが、経皮的に血中の酸素飽和度を調べる場合は、赤い光を照射してセンサーで血の色を読み取ります。
酸素がくっついているヘモグロビンはきれいな赤色だ、みたいなことは理科の実験とかでみたことがある方も多いかと思います。
人差し指の表側に赤色光と赤外光とを同時に照射するLEDを設け、裏側に受光センサーを置いておのおの強度を測定すると、両者の吸光係数の差によって受光センサーに到達する光の強度に差が生じます。
https://techfactory.itmedia.co.jp/tf/articles/1811/12/news001.html
実際のパルスオキシメーターは反対側にセンサーをつけますが、Apple Watchの場合は反射光で測定します。精度の問題はありますが、そもそも経皮的な酸素飽和度はざっくりとした呼吸状態を把握するくらいのものなので十分だと思います。
少し話はそれましたが、Apple Watchのセンサーが血管の色をみているということは、もう少し精度を上げれば静脈での生体認証も可能なのではないか、と思います。
個人認証が強固になればセキュリティの高い鍵になる
前置きが長すぎて自分でも何を書こうか忘れてしまいましたが、毛細血管だろうがなんだろうが認証方法はなんだっていいのですが、言いたいことは、「Apple Watchを身につけている人が本人であるということの証明」になるということが大事なのです。
Apple Watchを装着して、かつセキュリティ認証を突破していれば本人だと証明できたと考えていいと思います。すると、ロック解除されたAppleWatchを装着している人は、個人特定されているので、自宅の鍵や車の鍵を、近くに行くだけで解錠できるような仕組みに応用できます。
これは、ただ複雑な鍵であるというだけではなく、「本人しか持てない鍵」であることが大切なのです。ゲート側にも認証履歴が残りますから、例えばAmazon Goのような無人コンビニが世に広まったときに、Apple Watchさえ持っていれば、買い物は会計が入らなくなります。もちろん、個人が特定されているので悪いことはできません。

自宅の鍵を落としたら、誰でも使える鍵になるけど、鍵を落としても、個人認証が突破されなければ使用できないというのも大事ですね。
U1チップが利便性を加速させる
こんな感じで、セキュリティ上の観念で利用したいのが、U1チップ。これは、これまでの無線技術よりも格段に位置情報が正確に伝えられます。車の鍵がスマートキーの方なら想像しやすいと思いますが、私の鞄にスマートキーが入っていれば、近くにいる例えば子供でも、車のロックを解除できます。
これが、数センチ単位の位置情報でも正確に伝えられる技術だ(と仮定する)と、装着している人だけが鍵を開けられるという微調整が可能になります。発信する情報量もBluetoothよりも多いということですから、個人レベルでのセキュリティ範囲の調整なども容易にでき、自分が使いやすいようにカスタマイズも可能になりそうです。

とまぁ、好き勝手に書きましたが、活用の幅はずっと広いので、どうせ買うなら、Series 6がいいかもね、という話でした。

とは言え、自分が活用するタイミングで買い替えなどすればいい話なので、まずはSEを使ってみて、ウェアラブル端末の未来が感じられたら、ふさわしいタイミングでグレードアップしていけばいいと思います。
血中酸素濃度測定は、必要?

SEとSeries 6での大きな違いは、やはり目玉である血中濃度測定になると思います。つまり、SEにすべきか、シリーズ 6にすべきかは、あなたが酸素を測りたいかどうかで決めればいいと思います。

私は、今、このサイトでも「医療系ヘルスガジェットライター」を標榜しようと思っているので購入必須ですが、一般の人に果たして必要になるかどうかは吟味が必要です。
どんな人に便利なのか
今のところ、血中酸素濃度アプリで、現在の測定値を表示するだけの機能に収まりそうな予感がしますが、将来的には集めたデータを活用してユーザーに還元できるようなシステムが組み込まれるはずです。

ただ、実際のところ、酸素飽和度が測定できると何ができるのか、は知らない方も多いと思います。
医療では呼吸状態のざっくりとした評価
入院などしたことある人なら想像しやすいと思います。手術なんかしていれば実感もあると思います。人体のバイタルサインは体の状態を客観的に知るための指標として便利です。
SpO2やSaO2って何だ?
バイタルサインとして使用されるのは、(疾患と体の状態によりますが)心拍(脈拍)、呼吸数、表情・顔色、血圧、体温などがあります。酸素飽和度はSO2で示されるもので、測定方法によって「経皮的(SpO2)」や「動脈血(SaO2)」と表現されたりします。
簡易な方法として経皮的サチュレーションを測定するのですが、心電図モニターと一緒に、指などに赤い光を発するセンサーを巻いたりして常時観察に利用されたりします。
正常範囲と異常値
健康な場合はSpO2は99%とされていますが、センサーの当たり方や運動などによって低酸素とされる95%以下が表示されることはまずまずあります。というかしょっちゅうあります。

実際に呼吸苦が顕著に現れるのは、低酸素状態が疑われる90%以下と言われています。
呼吸も実際に目視で確認はしますが、胸郭がわかりやすく動いてくれるような呼吸状態の方ばかりではありません。むしろ、危険な状態の方は小さな呼吸でわかりづらかったりします。夜勤の見回りではいつも冷や冷やしています。
呼吸は止まったら即急変するので、SpO2のようなセンサーを利用した測定でバイタルサインを確認したりするわけです。
コロナでの実用性に関しては言及しない
ざっくりApple Watchの情報を調べるために他の記事も見渡したりしたところ、「コロナの発見に役立つ」みたいな海外記事もありました。当然、健全な会社であるAppleはこんなことは公表しません。むしろ酸素飽和度測定アプリは医療行為として使うものではないと明言しています。
この機能は、医療での使用や医師との相談または診断を目的としたものではなく、一般的なウェルネスとフィットネスのためだけに使えます。
https://www.apple.com/jp/apple-watch-series-6/
確かに、コロナに感染したら呼吸状態が悪くなるのでApple Watch上でも酸素飽和度の低下が観察されると思います。ただ、その前に周辺症状として発熱・倦怠感・味覚鈍麻などみられているはずなので、Apple Watchの酸素濃度低下アラートを待つまでもなく、PCR検査を受けるべきです。
重症者が入院できない時の判断材料なら、あるいは
ただ、もし、今後医療機関がパンク状態になって、重篤な感染状態であっても自宅待機せざるを得ないという状況下で、自宅の高齢者の呼吸状態が思わしくないときに、このような低酸素アラートで介護者が救急車要請の判断に役立つ、という状況はあるのかもしれません。

とは言え、あくまでも医療的にはApple Watch での酸素飽和度計測は補助的な機能だとして、あてにしすぎない方がいいと思いますけどね。
というわけで、基本的には医療系での活用はあまり考えない方向性でいきたいと思います。
眠りの質を確かめる
これまでも、睡眠トラッキングとしてApple Watchは活用されていました。その他のスマートウォッチも含めて、最新のスマートウォッチ事情をまとめた記事はこちらをどうぞ。
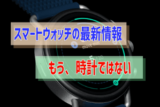
Apple Watchならこれまでのセンサーでも測定可能
睡眠の質の測定には、速度計などの各種センサーを使って、寝返りの回数などで眠りを評価していたみたいです。さらに、心拍数も測定できるようになって、睡眠の深さ(心拍数が減る)なども測定できるようになりました。
重大な睡眠時無呼吸はSpO2が著明に低下
ここに、酸素飽和度も加わることで、睡眠時の呼吸状態が計測できるようになります。これは言い換えると、睡眠時無呼吸(SAS)の有無や程度を把握することにもつながります。
あくまでも、自身の呼吸状態から、無呼吸症候群である可能性をモニタリングしていくまでがApple Watchでできること。診断や治療に関しては呼吸器系の医師との相談になります。
SAS放置は、本人にも周囲にも影響が
ちなみに、SASの患者は日本にもかなりいるのですが、未治療がほとんど。
しかし、日中の集中力にも影響するため、過去には命に関わる事故につながることもありました。
本人の睡眠の質もそうですが、夜間に呼吸が停止すれば当然危険ですし、合併症が進行している可能性もある、重篤な疾患です。
夜間の急激なサチュレーションが継続して起こっているようなレコードが出るようであれば、医療機関への受診のきっかけになるかもしれません。

ちなみに、肥満や高血圧、糖尿病などのが疾患リスクとして挙げられているので、総合的なヘルスケアの必要性を痛感する結果になる方も多そうですね。
登山時の高山病症状の目安に
登山や高所トレッキングには、酸素不足による急性高山病の危険性が常に伴います。
私自身は登山はしないので、危険性の周知くらいしかできませんが、高山病は比較的無症状で始まり、しかし場合によっては脳浮腫・肺水腫などの致命的な症状が出現する可能性もあります。

低血糖なども気づいたときには意識不明に、なんてことがあるくらいですから、登山中の体調の変化には注意したいところですね。
Apple Watchは酸素飽和度を測定してくれて、かつ低酸素状態でアラート通知することも可能です(要確認。諸サイトに記載ありますが、公式HPでは心拍数でのアラートはありますが、SpO2定価でのアラートに関する言及は見つけられていません。十中八九、心拍にも影響はでますけどね)。
AppleWatchが高山病の診断ができるわけではありませんが、登山のペースを調整する目安になるかと思います。
同様に、航空機での移動が多いスタッフや搭乗者にも有効
気圧の低下に伴い機内酸素分圧(空気中の酸素の圧力)も地上の約80%となります。呼吸器の障がい、心臓の障がい、脳血管の障がいや重症貧血などは酸素濃度の低下により影響を受けます。また、妊娠後期の妊婦や新生児にも酸素不足が悪影響をおよぼすことがあります。
https://www.jal.co.jp/jalpri/aircraft/environment.html
飛行機で体調が悪くなりやすい方など、酸素飽和度の変化を見ながら意識的に呼吸法を工夫したり、添乗員のかたに体調不良を伝えるなどの対応を考えるきっかけになりそうです。
人間が高度 1 万 ft 以上の環境に晒されると、酸素不足の現象が起こってきます。この時、呼吸数を増やしたり、深呼吸をしても全く効果は期待できません。逆に、呼吸のバランスを崩すことにより、二酸化炭素濃度 が低くなりすぎることによる弊害すら出てくる可能性もあります(過呼吸症候群)。
https://aeromedical.or.jp/circular/pdf/28gou.pdf
特に、低酸素症状では、意識が不鮮明になったり判断力が落ちたりするので、周囲の人にも客観的に状態を伝えられる方法があるのはいいことですね。
通常、与圧された航空機では高度 2,400m 程度の客室圧力高度を保持しており、低酸素症はほぼ発生しないが、与 圧されていない場合約 3,000m で SaO2 が 90%を示すため、高度 3,000m 以上で与圧なしで飛行すれば、低酸素症 になる可能性は存在する。したがって航空機で救急患者を搬送する場合には、酸素投与を行うことが必要である。
https://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/circle/18/c9073.pdf
低酸素症状メモ
- a) 呼吸器系の反応
高度 1,200〜1,500m 以上で過換気症状がみられる。PaCO2 が低下して呼吸性アルカローシスの原因に。 - b) 中枢神経系の反応
脳血管が収縮し脳血液量が減少。初期症状は、興奮、不穏から軽度の精神障害、軽度の傾眠状態、判断力の低下、夜間視力の低下等。 - c) 心血管系の反応
SaO2 が 90%程度の低酸素状態では、血圧は軽度増加する。中等度の低酸素症では呼吸数が増加し、心拍出量が増加。低酸素が継続すると、肺動脈の血管攣縮を起こして、肺水腫、徐脈、低血圧を来す。
低酸素トレーニングで自分を追い込む
私は医療者なので、正直、一般の方がアスリートのようなレベルでトレーニングをするのは「リスク」しか感じないのですが、一応用途としてはお伝えしておきます。
2013年以降の研究で、球技の選手や陸上の短距離選手でも低酸素トレーニングによる効果があることがわかってきたんです。今では長距離種目だけでなく、さまざまな競技の選手が低酸素トレーニングを取り入れています。
https://www.asics.com/jp/ja-jp/blog/article/hypoxia-training
ダイエット効果も高まる?
低酸素下での運動中は普段よりも糖を多く使い、運動後は脂肪を多く使うようになるということ。もうひとつ最近わかってきたのが、いつもより食欲が減るということです。
https://www.asics.com/jp/ja-jp/blog/article/hypoxia-training
ダイエット系の記事にすると、なんだか怪しいアフィリエイト感が強くなるので、効果があるらしいですよ、くらいの情報で受け止めてください。
全く興味がなかったらApple Watch SEがおすすめ
ものすごくだらだらと酸素飽和度の利用方法について書いてしまいましたが、全く気に留めずにスルーと読み飛ばせた方は、Apple Watch SEがおすすめです。
前述の通り、Appleの広域無線チップであるU1が搭載されていないのは少し残念ですが、この辺りは他のデバイスが対応して連動する必要性を感じたら、新しいApple Watchを買えばいいと思います。周辺ガジェットが対応するのに数年はかかると思います。


















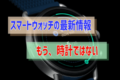

コメント
「factor meals ready」に関する最新情報です。
タイトル: Factorのレディメイドミールレビュー (2025)
Factorのレディメイドミールは、以前よりも大幅に改善されているようです。冷凍されていない、加熱するだけの食事は便利で、特にタンパク質の質感が驚くほど良好です。エアフライヤーやトースターオーブンを使用することで、より良い仕上がりになりますが、依然として電子レンジに頼る必要があります。
Factorの食事は高価で、1食あたり12ドルから15ドルで、最低6食の注文が必要です。メニューは週に45種類から選べ、特にケトやカロリー制限の食事に対応しています。しかし、過去のレビューでは、食事の質感が悪く、特にケト向けの料理が水っぽいと批判されていました。
最近、HelloFreshがFactorを買収してから、メニューはより食べ応えのあるものに進化しています。例えば、ポテトウェッジやアルデンテの米などが追加され、食材の質感が改善されています。ただし、コストや再加熱による食事の質の低下は依然として課題です。
全体として、Factorは便利さと多様性を提供していますが、価格が高く、全ての食事が新鮮な料理と同じレベルには達していません。特に、電子レンジ以外の調理器具を使うことで、より良い結果が得られる可能性があるため、今後の進化に期待が寄せられています。評価は6/10です。
https://www.wired.com/review/factor-ready-to-heat-meals/
「搬送 惣菜 工場」に関する最新情報です。
株式会社GEクリエイティブは、惣菜・弁当工場に特化した2機種の自律走行搬送ロボット(AMR)『YT-350F』と『YL-250F』を発表しました。これらのロボットは、エレベーターを利用して冷蔵庫や冷凍庫への自動搬送が可能で、業界初の取り組みです。特に、食品工場特有の課題に対応するため、大径タイヤやボギーアーム構造を採用し、傾斜や段差を克服する能力を持っています。また、ドーリーの自動連結や切り離し、現場での自動充電も可能です。これらの技術は、経産省の「令和6年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」に基づいて開発されました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000122630.html
「養殖 陸上 陸上 養殖」に関する最新情報です。
宮城県と東日本電信電話株式会社(NTT東日本)は、2025年1月21日にスマート陸上養殖の普及に関する連携協定を締結しました。この協定は、海洋環境の変化による漁獲量の減少や養殖生産の不安定化といった地域課題の解決を目指し、先進的技術を活用した陸上養殖技術の普及を通じて持続可能な水産業の発展を図るものです。具体的な連携事項には、ICTの活用、省エネ化、再生可能エネルギーの推進などが含まれ、両者は今後も相互連携を強化し、陸上養殖事業の効率化に向けた取り組みを進めていく予定です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001095.000098811.html
「canoo furloughs factory」に関する最新情報です。
EVスタートアップのCanooは、資金調達に苦しむ中で82人の従業員を一時解雇し、オクラホマ州の工場を稼働停止にしました。会社は「様々な資本源との高度な協議を進めている」とし、緊急資金の調達を目指しています。これまでの一年間、Canooは複数回のレイオフや一時解雇を経験し、かつての本社であるロサンゼルスのオフィスも閉鎖しました。最高技術責任者や創業者たちも退任しており、CEOトニー・アキラが運営するベンチャー企業からの支援を受けています。
https://techcrunch.com/2024/12/18/canoo-furloughs-workers-and-idles-factory-as-it-scrapes-for-cash/
「呼吸数 安静 安静 呼吸数」に関する最新情報です。
株式会社RABOは、スマート猫首輪「Catlog」に新機能「安静時呼吸数」を追加しました。この機能は、猫の安静時の呼吸数を測定し、ストレスや体調不良(発熱、痛み、貧血、呼吸器や循環器の問題など)を早期に発見する手助けをします。呼吸数が35回/分を超えると、飼い主にプッシュ通知で警告を発信します。このアップデートは、猫と飼い主の生活の質を向上させることを目的としており、既存の体温変化のモニタリング機能と合わせて提供されています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000037478.html
「factory factory seconds seconds」に関する最新情報です。
タイトル: オールクラッドファクトリーセカンズセールの最終日
要約:
オールクラッドの鍋やフライパンは高品質で知られていますが、その価格も高めです。このセールは、オールクラッドの「ファクトリーセカンズ」をお得に購入できる貴重な機会です。ファクトリーセカンズとは、軽微な欠陥(傷や箱のへこみなど)がある製品ですが、性能には問題がなく、ほとんどがオールクラッドの限定ライフタイム保証が付いています。セールは定期的に開催され、最終日には特別な割引が適用されます。購入する際は、すべての販売が最終であることを忘れずに。セールの詳細やおすすめ商品も紹介されており、特に高品質なステンレス製のフライパンや鍋が注目されています。
https://www.wired.com/story/all-clad-sale-september-2024/
「味覚 toshi toshi yoroizuka」に関する最新情報です。
宮崎シーガイアの「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」で、2024年9月27日から10月31日までの期間限定で、Toshi Yoroizuka監修の秋の味覚を使用したスイーツが登場します。特に、栗やサツマイモ、かぼちゃを使ったメニューが楽しめます。9月27日には、鎧塚俊彦シェフがガーデンビュッフェ「パインテラス」に来店し、特別なスイーツプレートを提供します。スイーツは950円で、風待ちテラスで楽しむことができます。秋の味覚を活かしたリゾートステイを満喫できるイベントです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000229.000017658.html
「陸上 陸上 養殖 養殖」に関する最新情報です。
関西電力の子会社がエビの陸上養殖に成功し、年間80トンの生産規模を持つプラントを運営している。関西電力はエネルギー供給に加えて食にもフォーカスし、社会貢献を考えている。陸上養殖は異業種参入であり、低コスト運用と生産性向上により黒字化が見込まれている。今後は高級飲食店向けに販売し、スーパーにも展開する予定である。水産事業の人脈づくりにも力を入れており、地道な積み上げが重要視されている。
https://japan.cnet.com/article/35219227/
「入院 世話 絞殺」に関する最新情報です。
アメリカ・ミズーリ州で、高齢男性が入院中の妻を絞殺した罪に問われている事件が発生。76歳の夫は「もうこれ以上は妻の世話ができないし、医療費も払えなかった」と供述。妻は透析治療のために入院中で、夫は妻の首を絞め、口と鼻をふさいだことを認めている。夫は過去にも2度妻を殺そうと試みており、動機は精神的な落ち込みと医療費の支払い困難を挙げている。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_663c3768e4b06eb9c982e0f2
「illinois rivian factory」に関する最新情報です。
リビアンは、イリノイ州から8億2700万ドルのインセンティブパッケージを獲得し、次世代電気自動車R2の製造を支援するために既存工場を拡張することを発表しました。この資金は工場の拡張、インフラ整備、従業員の職業訓練プログラムの強化に使用され、工場の更新は数か月以内に開始される予定です。
https://techcrunch.com/2024/05/02/rivian-827-million-incentives-r2-illinois/
「糖尿病 アプリ 活用」に関する最新情報です。
2024年3月15日に発表された研究によると、持続血糖測定を活用したスマートフォンアプリを使用した保健指導が、糖尿病予備群の体重と血糖値の改善に効果的であることが示された。新しい2型糖尿病予防のプログラムは食生活、体重、血糖値の改善に貢献し、今後の予防対策に期待される。アプリの改良や実際の予防効果確認のための臨床研究が進められる予定であり、効果的な予防対策の実現が目指されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000051296.html
「糖尿病 アプリ 活用」に関する最新情報です。
新潟大学とSOMPOひまわり生命保険などの研究グループは、持続血糖測定を活用したスマートフォンアプリを開発し、糖尿病予備群の体重と血糖値を改善する効果を示した。このアプリは食生活や体重、血糖値の改善に効果があることが明らかになり、2型糖尿病予防に活用される可能性がある。今後はより多くの人を対象にした長期の研究や臨床研究が必要であり、改良と効果の確認が進められる予定だという。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vcHJ0aW1lcy5qcC9tYWluL2h0bWwvcmQvcC8wMDAwMDAwNzUuMDAwMDUxMjk2Lmh0bWzSAQA?oc=5
「ダイエット 用賀 ダイエット パートナー」に関する最新情報です。
『ダイエットパートナー 桜新町・用賀店』は、用賀駅から徒歩10分の場所に位置し、パーソナルトレーニングジムとしてオープンしました。無料体験も受け付けており、業界トップクラスの料金設定でダイエット成功者を目指すことを掲げています。完全予約制の個室でマンツーマントレーニングを提供し、初心者や女性にも優しい環境を提供しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000057578.html
「浮腫 リンパ リンパ 浮腫」に関する最新情報です。
有明病院とZOZOは、がん術後のリンパ浮腫患者の手足の周囲を測定するために、ZOZOSUITと専用のスマートフォンアプリを使用した検証を行った。リンパ浮腫はリンパ液の流れが滞り、四肢にむくみが生じる病状であり、早期発見と介入が重要であるが、診察施設が少なく、介入が行き届いていないという問題がある。この検証により、簡単かつ高精度にリンパ浮腫を測定できる可能性があることが分かったと述べている。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2401/29/news151.html
「鉄道 富士 富士 登山」に関する最新情報です。
山梨県の「富士登山鉄道構想」に対して、富士吉田市は電動バスの導入を推進しています。富士吉田市は、2013年に世界文化遺産に指定された富士山の課題解決策の一つとして、電動バスを提案しています。富士吉田市は、インターネットで行ったアンケート結果によると、富士登山鉄道に対して「反対」と「どちらかといえば反対」が63%であり、「賛成」と「どちらかといえば賛成」が37%でした。ただし、このアンケートはインターネット利用者に限定されているため、結果には注意が必要です。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2401/27/news033.html
「技術 通信 味覚」に関する最新情報です。
ドコモは、通信技術を使って「味覚」を共有する技術を開発しました。この技術は、料理やワインの味を再現するために味覚調合装置を使用しています。ドコモの展示イベント「docomo Open House ’24」では、実際にこの技術を体験することができました。ドコモならではの工夫は、味覚の通信を「情報の意図」を伝えることにあります。これにより、通信を介して味覚を共有することが可能になります。この技術は、2023年から2024年にかけて実用化される予定です。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2401/17/news107.html
「狼山 民話 登山」に関する最新情報です。
福島県新地町の海ノ民話「鹿狼山の手長明神」特別デザイン手ぬぐいが、鹿狼山元旦登山会場で1000名に限定配布されました。このイベントは、福島県新地町で毎年行われる元旦登山イベントと合わせて開催され、参加者には限定の手ぬぐいが配布されました。手ぬぐいのデザインは、海ノ民話「鹿狼山の手長明神」とコラボレーションしたもので、かわいいデザインが人気を集めました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002343.000077920.html
「ダイエット ダイエット 始め 始め」に関する最新情報です。
編集部の2人がダイエット部を始め、それぞれの記録を公開しています。西村さんはカロリー記録アプリ「カロミル」を使って2kg痩せたと報告しています。松川さんはあすけんの女さんの笑顔が見たくて頑張っていたら痩せたと述べています。ダイエット部では、家電やウォッチなどのアプリを駆使して食事や運動の習慣を決め、実行しています。メンバーはLINEで報告し、活動の結果を共有しています。部員の一部は2kg痩せたと報告しており、体組成の変化も現れています。また、カロリー記録アプリ「カロミル」を使って食事のカロリーや栄養素を細かく記録し、体重の変化を把握しています。さらに、Fitbit Sense 2を使って1日の歩数を記録し、夜には筋トレも行っています。ダイエット部のメンバーは、自身の体質や生活に合わせた食事や運動を取り入れています。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/topic/topic/1540483.html
「共有 味覚 技術」に関する最新情報です。
NTTドコモと明治大学が、相手の感じ方に合わせて味覚を共有する技術を開発しました。この技術は、人間の味覚をデータとして蓄積し、他者との情報連携を通じて味覚を再現することが可能です。具体的には、触覚や味覚などの五感情報を共有することで、相手に自分の味覚を伝えることができます。これにより、遠く離れた人とも味覚を共有することができるようになります。この技術は世界初のものであり、将来的にはさまざまな分野で活用されることが期待されています。
https://japan.cnet.com/article/35213148/
「味覚 共有 技術」に関する最新情報です。
NTTドコモ、明治大学(宮下芳明研究室)、H2Lが共同で開発した味覚を共有できる技術が「docomo Open House’24」に出展されることが発表されました。この技術は、バーチャルな体験などで視覚や聴覚に加えて、味覚の再現も可能になるとされています。具体的には、センシングデバイスやアクチュエーションデバイスなどを使用し、個人の味覚感度や個人差を推定し、味覚データを共有することができます。これにより、言葉や表現だけでは伝えきれない味を相手に伝えることができるメタバース空間や映画、アニメなどのコンテンツで味覚の共有が行えるようになると期待されています。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2312/22/news113.html
「jal apple 製品」に関する最新情報です。
日本航空(JAL)は、マイルを使ってApple製品を購入できるEC店舗をオープンしました。この店舗では、iPhoneやiPad、Macなどの製品をJALのマイルで購入することができます。また、JALお買いものポイントも利用することができます。このサービスは、JALモールというオンラインショッピングモールで提供されています。JALのマイルを1ポイント1円として、アップル社製品を購入することができます。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LmF2aWF0aW9ud2lyZS5qcC9hcmNoaXZlcy8yOTA1MjTSAQA?oc=5
「指紋 センサー センサー 指紋」に関する最新情報です。
香港城市大学と米ジョージ・メイソン大学の研究者らが、スマートフォンのディスプレイ内の指紋センサーから指紋データを復元する攻撃方法を提案しました。この攻撃では、3Dプリンタを使用して偽の指紋を作成し、被害者になりすますことが可能です。この攻撃はサイドチャネル攻撃と呼ばれ、指紋データを盗むために特定の電磁波を使用します。この研究結果は、スマートフォンの指紋センサーのセキュリティに関する重要な問題を浮き彫りにしました。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2312/11/news014.html
「飛行 レベル レベル 飛行」に関する最新情報です。
東京都で、国内初となるドローンレベル4飛行で医薬品を輸送するプロジェクトが実施されることが発表されました。このプロジェクトは、2023年12月8日から18時までの間に行われます。飛行ルートは檜原村を含む都内の有人地帯上空を設定し、最大3往復の飛行が予定されています。このプロジェクトは、ドローンを活用した医薬品の輸送に関する国内初の試みであり、ドローンレベル4飛行の実証実験となります。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004820.000052467.html
「セキュリティ セキュリティ ベンダー ベンダー」に関する最新情報です。
セキュリティベンダーの選定には注意が必要です。組織の中核となるセキュリティシステムを単一のプロバイダーに絞って構築することは簡単かもしれませんが、必ずしも最善の選択肢とは限りません。セキュリティプロバイダーを選ぶ際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。
セキュリティツールの購入と食料品の購入には共通点があります。安価な製品やベンダーを選ぶことは魅力的かもしれませんが、品質や信頼性に問題がある可能性があります。セキュリティに関する重要な決定をする際には、価格だけでなく、品質や信頼性も考慮する必要があります。
製品やベンダーの統合は、選定に大きな影響を与えることがあります。異なる製品やベンダーが統合される場合、互換性やセキュリティの脆弱性などの問題が発生する可能性があります。統合の影響を事前に評価し、問題がないか確認することが重要です。
セキュリティベンダーの選定には慎重さが求められます。組織のセキュリティを守るためには、信頼性の高いベンダーを選ぶことが重要です。価格だけでなく、品質や信頼性
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2311/05/news004.html
「入院 患者 入院 患者」に関する最新情報です。
ビーマップは、入院患者向けの有料Wi-Fiサービスを11月1日に開始することを発表しました。このサービスは、入院患者の孤独を軽減するために提供されるもので、手軽に導入できるビジネスモデルです。ビーマップは、病院側がWi-Fi設備の構築や運用にかかる費用を負担し、入院患者が有料でWi-Fiにアクセスできる仕組みを提供します。また、ビーマップは、光コラボレーション「BeMap 光」の提供も開始し、高速で高品質なインターネット接続サービスを提供します。これにより、病院側は一部の収益を得ることができます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000018483.html
「apple apple iphone factory」に関する最新情報です。
このウェブサイトは、Apple iPhoneの工場出荷時のリセット方法についての情報を提供しています。記事の中では、Apple iPhoneのリセット手順や注意点について詳しく説明されています。また、ビジュアルストーリーやトレンドニュースなど、さまざまなトピックに関する情報も提供されています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMibGh0dHBzOi8vdGltZXNvZmluZGlhLmluZGlhdGltZXMuY29tL2dhZGdldHMtbmV3cy9ob3ctdG8tZmFjdG9yeS1yZXNldC1hcHBsZS1pcGhvbmUvYXJ0aWNsZXNob3cvMTA0ODExMDY3LmNtc9IBcGh0dHBzOi8vdGltZXNvZmluZGlhLmluZGlhdGltZXMuY29tL2dhZGdldHMtbmV3cy9ob3ctdG8tZmFjdG9yeS1yZXNldC1hcHBsZS1pcGhvbmUvYW1wX2FydGljbGVzaG93LzEwNDgxMTA2Ny5jbXM?oc=5
「ウォッチ 呼吸 睡眠」に関する最新情報です。
韓国のサムスン電子は、ギャラクシーウォッチシリーズに「睡眠時無呼吸早期発見」機能を追加する予定です。この機能は、睡眠中に無呼吸が起きた場合に早期に検出し、支援するものです。来年初めにサムスンのヘルスモニターアプリのアップデートを通じて、ギャラクシーウォッチ5とウォッチ6で利用できる予定です。この機能は、ギャラクシーウォッチのバイオアクティブセンサーを使用して、睡眠中の血中酸素飽和度(SpO2)や睡眠呼吸指数(AHI)などを測定し、睡眠時無呼吸の症状の有無を推定・計算します。これにより、睡眠時無呼吸の早期発見と対策が可能となります。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vbWVkaWEuZGdsYWIuY29tLzIwMjMvMTAvMDcta29yZWF3YXZlLTAxL9IBNGh0dHBzOi8vbWVkaWEuZGdsYWIuY29tLzIwMjMvMTAvMDcta29yZWF3YXZlLTAxL2FtcC8?oc=5
「選手 山中 日本」に関する最新情報です。
山中亮平選手が日本代表に緊急招集されたことが報じられています。彼は負傷したマシレワ選手の代わりに招集されました。山中選手はフランス大会で日本代表のメンバーに漏れたことを諦めず、2027年のワールドカップを目指してラグビーの第3章をスタートさせる決意を表明しています。彼は子どもたちに勇気を与えるヒーローのような存在であり、彼の姿を見て子どもたちはショックを受けて泣いてしまったと言われています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65086efbe4b0584d7c6bcba6
アマゾンは、Kiva Systemsの買収後、大量のロボットを導入し、倉庫内でのタスクを自動化しています。Proteus、Cardinal、Pegasus、Robinなどのロボットは、倉庫内で商品をピックアップし、大型のコンテナに入れたり、配送用のトラックに積み込んだりすることができます。これにより、アマゾンは効率を上げ、作業時間を短縮し、人件費を削減することができます。アマゾンは、AI技術の進歩により、ロボットの機能を向上させ、より高度なタスクを実行することができるようになっています。しかし、ロボットの導入により、多くの人々が仕事を失う可能性があります。アマゾンは、ロボットと人間が共存する未来を目指しています。
https://www.wired.com/story/amazons-new-robots-automation-revolution/