まず、運転をしていると気になるのが「最近、イヤホンしながら運転している人が多い」ということ。今回は、運転中に適度な音量で安全に音楽を楽しむことができるウェアラブルスピーカーという形状について強くお勧めしたいと思っています。
車内に持ち込めるお勧めのスピーカー

そもそも、車にスピーカー持っていく必要なくない? 標準でスピーカーついているじゃん。
そうお考えの方も多いでしょう。ただ、序文でご紹介したように、車内で音楽を楽しむのに「イヤホン」を使用するなど危険運転につながる行動が多く見受けられます。

家の車ならいいんだけど、社用車にスピーカーついてなかったり、スマホの接続に対応してなくて音楽が聴けない
という方は多いのではないでしょうか。
この記事では、一つの解決法として「ウェアラブルスピーカー」を紹介しますが、まずはその理由から。
車で利用するためのスピーカーのポイント
- 携帯性
- 車内での充電に対応
- 低音調整
- バランス
車内標準搭載のスピーカーは使用しない
これには3つの理由があります。
- カーナビの音量との兼ね合い
- 低音が弱い
- 車のスピーカーのグレードを上げるのは大変
スピーカーのグレードを上げるという手もありますが、車載スピーカーで音楽を楽しもうとすると、どうしても余計なお金がかかってしまいます。今回は、あくまでも手軽に、今乗っている車で、スマホを利用して楽しく音楽を楽しみたい方にお勧めしたい方法です。
ウェアラブルスピーカーが最適
全ての要件を満たし、安全な運転の妨げにならないのが、ウェアラブルスピーカーです。今回の「車で使用する」という条件に沿った商品として、KENWOODを紹介していますが、とにかくまずは安全性についてよく検討してみてください。
これまで利用していたBluetoothスピーカー
私がウェアラブルスピーカーにたどり着くまでに試したスピーカーのお話。代替案としてはありっちゃあり。
BOSEのCHARGE3
先ほど車内にも持ち込めるスピーカーとして大事なポイントを申し上げましたが、半分以上の要件は満たしております。
- 片手に乗るくらいのサイズ感
- USB充電可能な上に容量
- 低音の微調整はできないが十分なサウンドクオリティ
ただ一つ、使用していてどうしても気になる難点が、設置に関することですね。
難点は「転がる」
家で使う分には、申し分ないグリップ感で、底面はゴム製なので滑ったりはしません。ただ、運転となると少し心配になるのが、ブレーキ時に転がることです。運転に関しては、転がったChargeがブレーキに挟まると本当に危ないので、「別途しっかりと固定する」か、「転がっても安全な場所に置く」の選択を余儀なくされます。
固定したらChargeの魅力が激減
しかし、「防水」で「ポータビリティ」が良いのがChargeの売りなのに、車に固定してしまってはもったいない。後部座席に置いたら反響音と車外の雑音が混ざってしまう。
ということもあって、今回はウェアラブルスピーカーをお勧めしたいと思ったわけです。
メーカー別お勧めのウェアラブルスピーカー
さて、メインコンテンツのお勧めのウェアラブルスピーカーです。前述の通り、「運転中」がキーワードですので、選定の軸は「安全性」です。
色々な用途で考えている場合には、SONYやBOSE、コスパで選ぶならJBLやSHARPもあります。チャレンジできるならDoltechという5000円台のものも比較対象としてあげてみました。
ケンウッド KENWOOD
車載スピーカー関連に強いケンウッドが、満を辞してリリースしたウェアラブルスピーカー。
- スマホに最適化
- aptXに対応
- ハンズフリー通話
- 音声認識機能
音質も安心のKENWOOD製

安いスピーカーってなぜ迫力がないのかっていうと、スピーカーのサイズの問題と、音の作り方の問題があります。
当製品の場合、パッシブラジエーター搭載なので、幅広い音質に対応することができます。振動が気になる方もいますが、私の場合は、音楽の一部として「体感する」ことが楽しい機種だと思います。
珍しい「車内でも使用できる」を売りに
運転中の使用に関しては、他社製品だと「危険だからやめてくれ」と書かれていることが多い。ですが、KENWOODは「ドライバー」にも向けたメッセージとして、
車の中でも安心安全に使用可能
https://www.kenwood.com/jp/products/car-accessories/speaker/cax-ns1bt/
運転中でも耳を塞がずに首にかけるだけでハンズフリー通話が可能。「Siri」なdの音声認識機能の起動にも対応。耳を塞がないから安心安全に使用可能。
という文面がみられます。何より、カーアクセサリに分類されてますからね。これが私が今回お勧めとして上げる理由です。

訴訟予防に「お勧めしない」と書くのは簡単だけど、自信を持って出せる製品であれば、こうしたアプローチはありだと思います!
軽いから本当に使いやすい
車で使用する想定では、やはり運転に支障が出るようなことはなるべく避けたいところ。

運転はただでさえ緊張するものだから、肩がこるんだよね
という方に朗報で、KENWOOD製は何より軽い。負担感が少ないとレビューでも多く見受けられます。
JBL
今回は上級メーカーのコスパ部門としてお勧めしたいのがJBLです。ただ、セールは狙って欲しいので、Amazonや楽天市場の動向と調整してください。
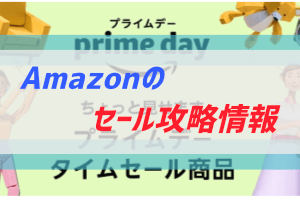
SOUNDGEARのコスパは異常
ちなみに、SOUNDGEARというのは、JBLのウェアラブルスピーカーの名前です。
これから、SONYとBOSEと言った、いわゆる同レベル(と私は考えている)メーカーも紹介しますが、概ねほぼ同音質、かつ高機能でありながら、お値段はぜひストアでご確認いただきたい。マジで安い。
深夜視聴には注意が必要
これはJBLの商品全体に言えるのですが、まず起動音の問題。JBLは一体どこで使用することを想定しているのかわかりませんが、少なくとも日本家屋で使用する場合、設定音、起動音、着信音などのボリュームが、かなり大きいです。

接続切れなどを知らせる音にビビる、というレビューが多いね
ちなみに私が愛用するCHARGEも爆音です。これはもう諦めるしかないのか。深夜視聴に向かないというのはウェアラブルスピーカーの利用目的としては少し侘しいところ。
SONY
とにかく、絶対に失敗しない商品を選びたい場合は、SONYがお勧めです。ウェアラブルスピーカーが人気を博すようになったのは、SONYのおかげと言っても過言ではない。
没入感が半端ない
SONYは未だ新しいスタイルを提案し続けてくれる日本の良き総合家電メーカーですが、ウェアラブルスピーカーに関しては、最初「ん?」と思った。正直、いや、それもうヘッドホンでええやんと。

生活に取り入れてみると「あかん、これは必需品や」と思わせてくれた、まさにエポックメイキングと言わざるを得ない。これまで音楽の体験といえば「音の世界に入り込む完全独立個体」として一人で楽しむ場面もあれば、スピーカーで同じ環境にいる全員で楽しむ場面しかなかった。いや、想像ができていなかった。つまり、個と集合体の2つの回答しか持ち得なかった既成概念に囚われた私に、「集合体としての個」としてのあり方を提案してくれた、まさに

まぁとにかく取り入れてみると意外と便利ってことで
2台送信可能は便利
送信機付きなのですが、この送信機でスピーカー2台に音を飛ばすことができます。想定するシチュエーションとしては、キッチンで料理をするママ、仕事で画面は見ないパパ、それに普通にテレビを見ながら音楽番組を楽しむ子供で同じ「テレビを見る」という体験を最上級化することができます。

テレビのボリュームだけで調整すると、ママは聞こえないし、パパは集中できない、なんてことはよくありますね。
ちなみに、SHARPなんかも同様の機能を搭載してますので、この機能だけで選ぶことはないですね。
振動を取り入れた体験
これはむしろゲームユーザーにお勧めしたいので、今回は割愛しますが、低音を出すために発生した振動を、リアルな体感として提供するというもの。
BOSE
音質の良さは折り紙つき
BOSEが気になってる方は、おそらくすでに何点かBOSEの製品をお持ちで体感されている方かと思います。少なくとも、BOSEユーザーを満足させる仕上がりであることはお伝えしてもいいでしょう。

私のように家電量販店でふむふむ言いながらのんびり試聴できないのが残念でしたが、私には上質体験でしたね。
BOSE Connect アプリで使い勝手もよし
https://www.bose.co.jp/ja_jp/support/article/bose-connect-app-pulse.html
何より高い
ネックとしては(ネックスピーカーだけに)、値段がかなり相応のものということです。逆に、この価格に抵抗ない人には一度BOSE体験はお勧めです。音質についても、つけ心地についても、上質体験にアップデートされており、「あぁBOSE買ってよかったな」と思わせてくれます。

私もお金があればBOSE一択ですね
SiriとGoogleアシスタント対応
そういえば運転中を想定した記事を書いていたと思い出したところですが、運転中の操作について考えた場合、SiriやGoogleアシスタント、Alexaといった音声認識ガイドについてはあるに越したことはない機能です。私個人としては、操作に気をとられるのは心配なところですが、スマホをいじるよりもよっぽど安全なので、やはり必要な機能といっていいでしょう。
防滴仕様
これは運動用ということになるのですが、運転中に汗をかきやすい方には必要ですね。防滴程度なので、滝のような汗には対応していないし、コンバーティブルで雨の中突き進む、みたいな使い方もダメやで。
SHARP
SHARPは紹介する予定になかったのですが、個人的に少しきになるところがありまして。少々お付き合いください。
総合メーカーとして安定の機能
- 本体:(幅)18.1cm×(奥行)18.1cm×(高さ)1.6cm
- 質量:約88g
- 音声出力:1.4W
- bluetooth4.1対応
- 充電時間:2.5時間
- 連続使用時間:約14時間
- 音声アシスタント:Googleアシスタント,Siri
- バイブレーション機能搭載
- 通話用マイク内蔵
少し手抜きですが、こんな感じで、まーバランスのいい製品仕様です。軽いし、仕様時間と充電時間も申し分ない。音声アシスタントもある。書いてないけど、デュアルストリーミングで2台あれば楽しみ方も広がる。

これ、SONY製の廉価版としていけるんでない?
Doltech
Amazon好きとしては一番お勧めしたいのがDoltechのネックスピーカー。
コスパ最上級
まず、失敗しても大きなダメージにはならない5000円付近のコストパフォーマンス。会社情報が見えてこないのが少し心配なところですが、その分、レビューはサクラではない本物の顧客からの情報がちゃんと寄せられています。
フジサウンド
私はこのご時世に社名検索をしてトップ検索されない会社はあまり信用していませんが、日本メーカーだということを信じてDoltechとの対抗馬にご紹介。
イヤホンとしても使えるハイブリッド展開
ウェアラブルスピーカーを探していると、このイヤホン付属型をよく見かけます。個人的にはイヤホンを使うときはイヤホンを使用するので不要ですが、「気軽に音楽を」と考えている方にはありですね。
Bluetooth送信機は別売り
ご注意を。手軽に楽しみたい方にとって、そもそもBluetoothって何だという方も多いと思いますが、ご自分の利用される機器がBluetoothに対応していれば送信機は不要です。最近のテレビやスマホはほぼ対応しているので心配は不要かと思いますが。
運転中に使用する場合の注意点
イヤホンは危険
法的解釈をみてみる
道路交通法 第70条(安全運転の意義)
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
というわけで、道路交通法としては、「イヤホン」に限局した制限、禁止措置は取られていません。
神奈川県道路交通法施行細則第11条 第5号(運転者の遵守事項)
「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
「周囲の音が入ってくる状態」が望ましい
当たり前ではありますが、密閉式のイヤホンの場合は外部からの音の遮断率を上げた構造になっているため、危険であると言わざるを得ない。

車の運転中って騒音ばっかりだから、気分を盛り上げるためにも騒音はシャットダウンしたい
という気持ちはすごくよくわかります。
仕事に向かう運転中が唯一の個室、プライベートな空間ですからね。大声で歌も歌いたくなるところです。
緊急車両のサイレンが聞こえない
とはいえ、やはり大音量で音楽を聴いていても緊急車両のサイレンが聞きづらくなるくらいですから、イヤホンを含め、スピーカーの使用方法には注意が必要であることはいうまでもありません。
スマホの利用について
そもそも、スマホを使用する機器は使わない方がいいんじゃないの?
ネットで情報を発信していると「多分大丈夫だろう」だけではダメだな、というのが当サイトの基本方針。気になったことは調べておきます。
道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
というわけで、「携帯電話の使用」についてはこんな感じに解釈されています。
スマホ運転と法律の解釈
- 停止(停車)時は利用できる
- スマホ画面を見つめるような、画像を注視する動作はNG
- スマホ本体を手に持つ動作はグレー
グレーゾーンとしてスマホ本体を「持つ」ことはセーフとする見解があります。何れにせよ、片手でスマホを手にとっている時点で運転から注意が外れているわけですから「法が正しい」としても運転に向ける姿勢としてはアウトと言っても良さそうですね。
















































































































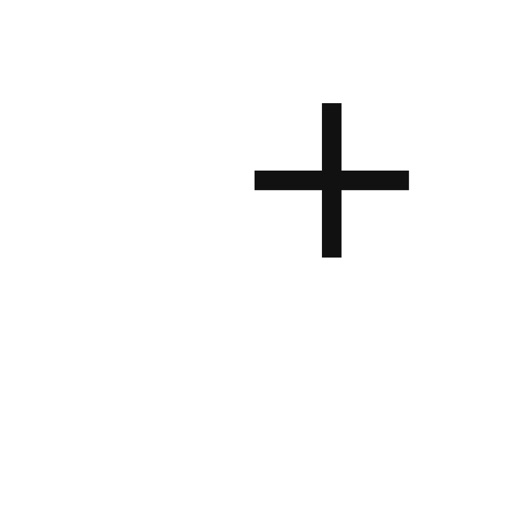















コメント
「jbl ケース 充電」に関する最新情報です。
JBL LIVE BEAM 3は2022年に発売されたJBLの完全ワイヤレスイヤフォンの後継モデルであり、ディスプレイ付きの充電ケースを搭載している。ハーマンインターナショナルが初となるハイレゾ対応のハイブリッドノイズキャンセリング機能も備えており、直販価格は2万8050円。JBL LIVE BEAM 3は完全ワイヤレスイヤフォンの新スタンダードと位置付けられており、使い勝手の向上が期待されている。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2407/05/news087.html
「pulse pulse スマートフォン スマートフォン」に関する最新情報です。
PULSE X7スマートフォンは、550ニットの標準照明条件下での画面輝度や2800ニットの最大輝度、6000mAhのバッテリー、120Wの高速充電機能など、革新的な機能を備えています。さらに、PULSE X7はPulse OSを実行し、5G接続をサポートし、生体認証セキュリティ機能も搭載しています。製造プロセスも環境持続可能性を考慮しています。PULSE X7は、高性能とコスト効果を両立させ、フラッグシップスマートフォンとの競争力を維持しています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMi6QFodHRwczovL3NtYXJ0cGhvbmVtYWdhemluZS5ubC9qYS8yMDI0LzA2LzE1LyVFNiU4QSU4MCVFOCVBMSU5MyVFMyU4MSVBRSVFOSVBOSU5QSVFNyU5NSVCMCVFMyU4MiU5MiVFNiU4RSVBMiVFMyU4MiU4QiVFRiVCQyU5QSVFNSU4NSU4OCVFOSU4MCVCMiVFNyU5QSU4NCVFMyU4MSVBQXB1bHNlLXg3JUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTlFJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTg4JUUzJTgzJTk1JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUIzL9IBAA?oc=5
「イヤフォン jbl ディスプレイ」に関する最新情報です。
JBLが、スマートディスプレイ搭載の充電ケースを持つ完全ワイヤレスイヤフォン「JBL LIVE BEAM 3」を発表しました。このイヤフォンはBluetooth 5.3接続に対応し、LDACコーデックを搭載しており、低音と中高音域を力強く再現します。充電ケースのバッテリー駆動時間はBluetooth接続時で約40時間〜48時間、LDAC接続時で約24時間〜36時間です。価格は2万8050円(税込み)で、ブラック/シルバー/ブルー/パープルの4色が用意されています。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2405/30/news123.html
「警視 靴底 びっくり」に関する最新情報です。
警視庁直伝の方法によると、雨の日に路面や店内で滑りやすい場合、靴底に絆創膏を貼ることで滑りにくくなるという。絆創膏を貼る際は、靴底をよく拭き取り、空気が入らないように貼ることがポイントとされている。この方法は2018年に発信され、再び注目を集めている。雨の日には路面での転倒事故に注意が必要であり、靴底に絆創膏を貼ることでリスクを減らすことができるという。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_664e9ec1e4b048d73b5548c2
「ローソン 撮影 道路」に関する最新情報です。
ローソンが富士山ローソンとして知られる人気撮影スポットにおいて、新たな対応道路の横断禁止を訴える看板を設置した。これは、安全対策の一環として行われ、撮影マナーの遵守や公衆マナーの呼びかけが含まれている。また、警察や行政と協力し、外部警備会社の専属警備員の配置も検討されている。同様の対応が別の店舗でも行われる予定であり、観光客に人気のスポットである一方で、撮影マナーの問題が発生していると報告されている。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2405/05/news038.html
「点検 道路 性能」に関する最新情報です。
スマートフォンによる道路点検システムGLOCAL-EYEZが国土交通省の性能カタログに掲載され、舗装点検と道路巡視の両方で最高ランクの精度を誇ることが報告された。このシステムはAIを活用し、車両の振動データと画像データを解析することで道路の損傷状況を評価し、効率的な道路管理を支援している。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000107939.html
「アナ 特番 フジ」に関する最新情報です。
フジテレビの特番「FNS明石家さんまの推しアナGP」が4年ぶりに放送され、35年にわたる女子アナ特番の伝統を持つことが分かりました。番組では、41人のアナウンサーが集結し、明石家さんまさんが新たなスターアナウンサーを発掘するコンセプトで放送されました。
https://toyokeizai.net/articles/-/749212?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「waymo traffic robotaxis」に関する最新情報です。
サンフランシスコのフリーウェイのオンランプへの交通を妨げる7台のWaymoロボタクシーが報告された。これはWaymo車両が交通を妨げる最初の記録された事件であり、これまでにも同様の問題が発生していた。サンフランシスコの公式は、ロボタクシーが道路を塞ぐ際に対処できず、違反切符を発行できないという課題に直面している。
https://techcrunch.com/2024/04/17/seven-waymo-robotaxis-block-traffic-to-san-francisco-freeway-on-ramp/
「jbl go jbl go」に関する最新情報です。
JBL GOシリーズの最新モデル「JBL GO 4」は、累計出荷台数5700万台を超える人気製品で、前モデル「JBL GO 3」から約4年ぶりのモデルチェンジとなっている。GO 4はコンパクトなBluetoothスピーカーで、ファブリック調のデザインが特徴。サイズはわずかに大きくなり、重量は17g軽量化されている。JBLは4月11日に「JBL GO 4」を発売し、価格は7700円で、全9色のカラフルな展開がされている。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2404/17/news084.html
「jbl スピーカー サイズ」に関する最新情報です。
ハーマンインターナショナルがポータブルBluetoothスピーカー「JBL GO 4」「JBL CLIP 5」を発表。コンパクトなデザインで9色のバリエーションがあり、価格はJBL GO 4が7700円、JBL CLIP 5が9900円。Bluetooth 5.3に対応し、防水/防塵(IP67)仕様。専用アプリ「JBL Portable」で管理やイコライザー調整が可能で、ワイヤレスステレオ再生や複数機器からの同時再生も可能。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2404/05/news115.html
「車両 武装 乗組員」に関する最新情報です。
デベロッパーのEvil Mangoが新作ゲーム『Railpunk Mayhem』を発表。プレイヤーは武装列車を走らせながら敵と戦うローグライクアクションゲームで、都市で停車してアップグレードや修理が可能。追加できる車両には武器車両や兵舎車両があり、列車には一般客を乗せた客車も存在する。
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20240318-286471/
「kenwood kenwood 車載 バッテリー」に関する最新情報です。
KENWOODが再生バッテリーを利用したポータブル電源「IPB01K」を発売。動作温度は-20℃から60℃まで対応し、約2,000回の充電が可能。価格は17万500円前後で、2023年度には「グッドデザイン金賞」を受賞している。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNWh0dHBzOi8vZGMud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTU3MDE2NC5odG1s0gEA?oc=5
「hate antisemitic antisemitic islamophobic」に関する最新情報です。
新しい報告書によると、Xは反ユダヤ主義やイスラム恐怖症の憎悪を放置していることが明らかになりました。中東の紛争が激化する中で、Xは穏健なヘイトスピーチを防ぐことに失敗し、反ユダヤ主義の陰謀論を広め、ヒトラーを称賛し、ムスリムやパレスチナ人を非人間化しています。
https://techcrunch.com/2023/11/14/x-is-leaving-up-antisemitic-and-islamophobia-hate-new-report-shows/
「セキュリティ 神奈川 ctf」に関する最新情報です。
富士ソフトは、セキュリティコンテスト「CTF神奈川」に問題作成で協力して、サイバー犯罪の対処能力の向上をサポートしています。このコンテストは、2023年11月17日に開催される予定で、富士ソフトは企業団体の1社として協力しています。CTF神奈川は、神奈川県警察や情報セキュリティ大学院大学などが主催し、セキュリティに関する最先端の知見を持つ学術機関や関連企業が問題作成に参加しています。このコンテストは、セキュリティに関する知識や技術を競い合う場であり、富士ソフトはセキュリティ分野での重点技術を持つことから、問題作成に注力しています。富士ソフトの取り組みは、サイバー空間の脅威に対する対処能力の向上を目指し、安全で安心なインターネット社会の実現に貢献することを目的としています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000061382.html
「チャレンジ 体験 家電」に関する最新情報です。
島根県江津市で行われている「パズル家電解体チャレンジ」は、技術の粋を楽しむ体験プログラムです。中高時代から電子工作に興味を持っていた教諭の中田さんと実習助手の津田さんが、家電の解体に挑戦しました。ラジオやミニ掃除機など、さまざまな家電を解体していく中で、火花が飛び散ったり燃えたりするなど、苦戦もありましたが、完成した時の喜びや思い出はほろ苦いものでした。この体験プログラムは、島根県江津市の江津工業高校で企画されており、興味のある人は参加してみると良いでしょう。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmNodWdva3UtbnAuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvLS8zNjk4MDbSATBodHRwczovL3d3dy5jaHVnb2t1LW5wLmNvLmpwL2FydGljbGVzL2FtcC8zNjk4MDY?oc=5