私の家づくりノートは、パソコンやスマホで完結させるものです。
印刷して自分の手で書き込むのは時間の無駄になることも。
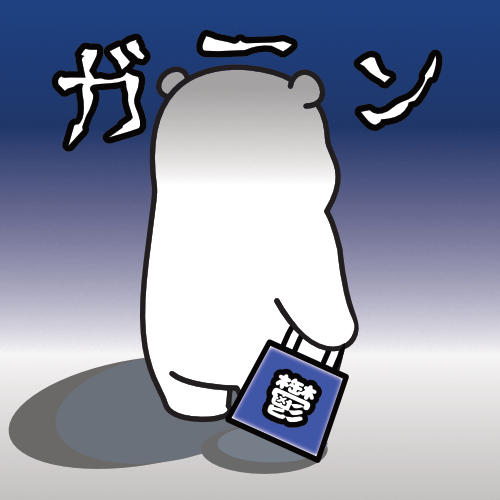
複数の住宅会社に提出するなら、コピーを取る手間が。。。
WordやExcelのデータを配布でもよかったのですが、Word・Excelの利用者も減っていますし。表などでまとめると、画像データを貼り付けた時にうまくいかなくて帰ってイライラさせるのも悪いなと思いますし。
今回は項目をコピペしてもらって、WordでもExcelでも、MacのPagesでも、あるいはスマホでnoteアプリでも。
全部に通用するように項目だけ書き出しました。ご自由にお使いください。
家づくりノートの簡単な作り方のポイント
今回は、あくまでも「簡単」を目標に作成していきます。
読者のあなたがやること
- Wordなどの文書ファイルにコピペ
- 内容をチェック(読むだけで学べるようにしています)
- 思いつかなかったら項目を消してメモスペースに
たったこれだけ。
基本となる4つの項目
- 予算
- デザイン
- 間取り
- 性能
基本はこの4つを掘り下げるだけです。基本的にはわからないものは消していってもらうだけでいいのですが、「予算」の未記入だけはやめましょう。
無料見積もりをとってもらう意味がなくなってしまいます。
一番大事な予算項目
まずは予算ですね。住宅の予算に関する内容はこちらは別の記事を参考に予算計画をしてみてください。
予算に必要なデータ
- 年収、月収
- 月間に貯金できる金額
- 用意できる現金・頭金
- 用意してもらいたい現金(住宅会社への要望)
予算項目で大事になるノート内容
予算は本当に大事です。
ここをしっかりしていると、住宅会社は「しっかりとした提案をしよう」となりますし、ここがあやふやだと「まずは吊り上げるだけ吊り上げよう」となります。
我々にとってもデメリットです。
こちらの記事でも書きましたが、無料見積もりを使えるのは、時間的にも体力的にも、精神的にも、3社が限度だと私の実体験が申しております。
予算と提示する内容がバラバラだと比較にならない
この大事な3社に同じ条件で比較できる見積もりを提供してもらうには、予算があやふやだと話にならないんですよね。
さらに、各社のアンケートシートを使ってしまうと、内容がバラバラになるかもしれないというリスクもあります。
あくまでも要望書はこちらのものを使用してもらいましょう。
予算に関する各項目の解説
自作家づくりノートのデメリットでもあるんですが、自分で作っておきながら空白にするとやる気と計画性が疑われます。
書きたくない項目は消してしまってください。空白は「無計画」っぽいので消しちゃったほうがいいです。
収入面は資金計画も相談するなら書いてしまった方がいい
資金計画まで依頼するようなら、少し恥ずかしい気もしますが、収入面も記入したほうが話は早いです。
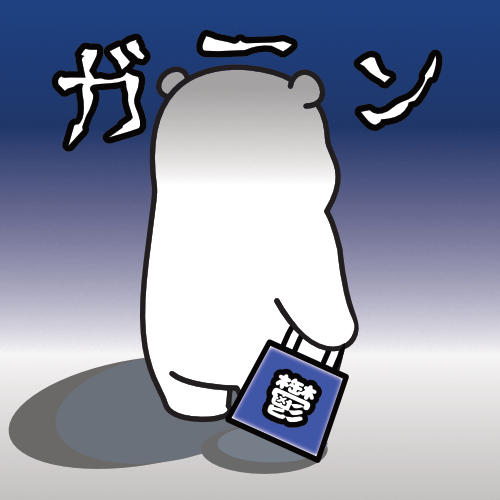
私はハウスメーカーに予算立ててもらうのはお勧めしませんけどね。
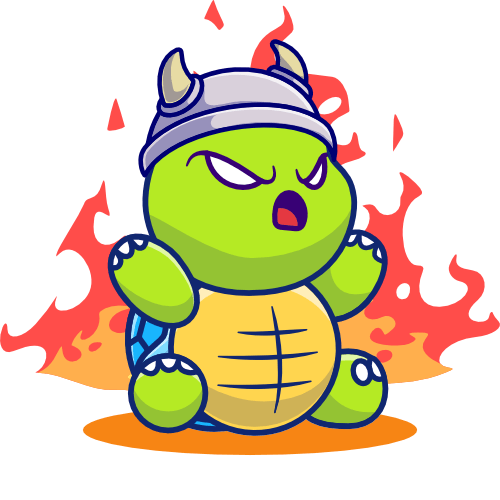
今の収入ならもっと大丈夫ですよ、とかいう営業は絶対に信用しちゃダメ。
職業は「ライフスタイル」項目でも重要なポイント
収入面では「安定性」と「上昇率」をみたりもします。ただ、収入としては必須ではない項目です。
土地の相談をするなら
住宅会社と土地不動産は懇意な仲ですので、土地の相談もしてもいいと思います。
会社によっては、立地がいい土地を抑えて、自社で建てさせる条件付きもあったりしますからね。正直、上物(家)よりも土地の方がよっぽど真剣に選ぶべきです。
予算項目のリスト
| 項目 | 内容 | 備考 |
| 家づくり全体の予算 | ( )円 | 予算に関しては別記事を参考にしてください |
| 年収 | ( )円 | 年収×5が安全圏です |
| 月収 | ( )円 | |
| ボーナス | ( )円 | ローンのボーナス払いはしない |
| 現在の貯金 | ( )円 | |
| 家づくり用のお金 | ( )円 | 貯蓄とは別で、家づくり用の現金です(諸経費で飛びます) |
| 頭金として使うお金 | ( )円 | 家づくり用から、頭金に当てる予定の金額です。見積もり時は無しでいいです。 |
| 用意すべきお金(メモ) | 住宅会社に「こちらではいくら用意すべきですか」と聞いておくと、諸費用の計算に役立ちます。 | |
| 職業 | ( ) | 特に伝えたいことがなければなしで。 |
| 土地 | あり・検討中・土地探し希望 | |
| 土地の要望 | ||
| 補足情報 |
コピーしてWordやExcelに貼り付けてください。うまくいかないときは、コピーを何度か試すか「貼り付け方法」を変えるとうまく表でコピーできます。
住宅に期待する性能
簡単ではありますが、解説を交えて説明していきます。
住宅性能に関わる家づくりノートのリスト
- 耐震性能
- 断熱性能
- 気密性能
- ZEH
- 省エネ
- 創エネ
耐震性能についての簡単な解説
住宅性能表示制度耐震等級で表されることが多いです。
- 耐震等級1:震度6強から7程度の地震でも耐えうる耐震性能がある。(倒壊・崩壊しない)数100年に一度。
震度5(数十年に一度)なら住宅は傷つかない程度。 - 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍でも大丈夫(学校や病院などの公共施設の基準)
- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の地震でも大丈夫。(防災施設の基準)
実は施主が決める耐震等級
耐震等級1は簡易なチェックでいいのですが、耐震等級2になると構造計算などやや複雑な検討方法になるため、1と2でいえば、2の方が信頼性は増すものだと思ってください。
ちなみに、「耐震等級3相当ですよ」とかいろいろな営業文句があるんですが、最終的に「耐震等級いくつにするか」を指示するのは施主です。というか、何も言わなければ「それ相応」の耐震性で建てられるだけです。
ただ、正式に耐震等級を証明する場合、いろいろお金がかかることがあるので、そこは要相談となります。「無理に証明までは必要ない」なら、安くすませることはできます。
耐震だけでは不十分、「制震」「免震」も確認を!
耐震は「倒壊しない」目安の、家の頑丈さ、硬さという「性質」の問題で、地震で安心かどうかは、もっと複合的な問題になります。
最近、よく「制震」「免震」という言葉が効かれるようになったように、「耐震性」は地震に対する安全性の、1部分にすぎません。
制振ダンパーの必要性
制振ダンパーは地震対策として取り入れやすいので、昨今ではさまざまな住宅メーカーが住宅商品に取り入れています。
断熱性能についての簡単な説明
取り急ぎ、断熱性能に関するページを作っておきました。

現在は施主に対して住宅性能の説明義務があるので、施主が無知でもある程度の品質の住宅に関しては確認しやすくなりました。
ちなみに、当サイトの断熱に関する情報は以下のリストの記事もあります。
とりあえず施主が注意しておくこと
これは個人的な意見ではありますが、昨今のエネルギー高騰と電気代の値上がりを考えても、まず優先すべきは「省エネ性能」であることは間違い無いとは思います。
その中で、何を優先して、何は後回しでいいのか、というのは難しいところです。簡単に言えば、住宅の断熱性能は「総合力」となるため、一部の断熱材だけを豪華にしても効果は感じづらいのが正直なところ。
特にリフォームなどにおいては「部分的な修繕」を行うこともあるとは思いますが、断熱材だけを詰め直して最新の良いものに変えても、窓が断熱できなければ外気の影響を強く受ける住宅のままとなってしまいます。
そうなってくると、断熱に関しては「あれもこれも」が必要となる要素となるため、言い換えると施主がどれくらいお金を出せるか、に依存するとも言えます。
そのため、いくら家の性能を高めた方がいいと言っても、知識がない状態で「とりあえず最高のものを」とすれば身の丈に合わない高額なローンを背負うことになり、一方で部分的に断熱性能を諦めて低コストに抑えようとすると「性能が発揮されない電気代が嵩む家」になってしまいます。
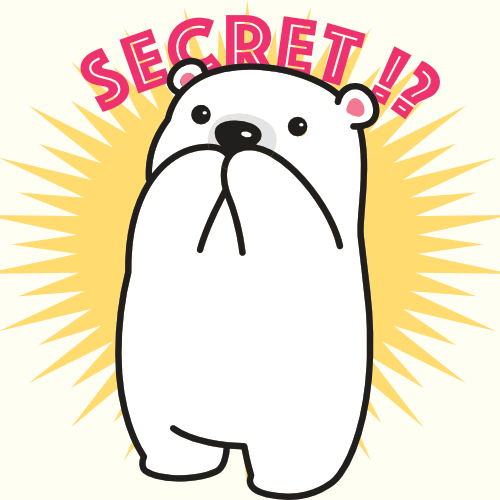
コスパと性能のバランスが一番シビアなのが断熱性能だと言えそうですね。
気密性についての簡単な補足
こちらは、ペットボトルの蓋がちゃんとしまっているか、という空気の交通量の性能を表すものです。隙間が少ないほど高得点。
先ほどのグラスウールの断熱材がどうしてだめかっていうと、グラスウール自体は断熱効果は高いのですが、ちゃんと密閉できてないと空気どころか熱も逃げるので、いくら断熱仕様が効果は薄くなります。
よく使われる比較できる数字は「C値」
気密性は住宅建築中に測ることができます。C値という値は「隙間」の広さを表しているので、気密性がいい場合は、数字が小さくなります。
目標の値がある会社なら、目標値が出るまで何度でも施工し直してもらいましょう。気密性は、断熱効果だけではなく、換気や結露予防などの、家全体の機能に影響を与えます。
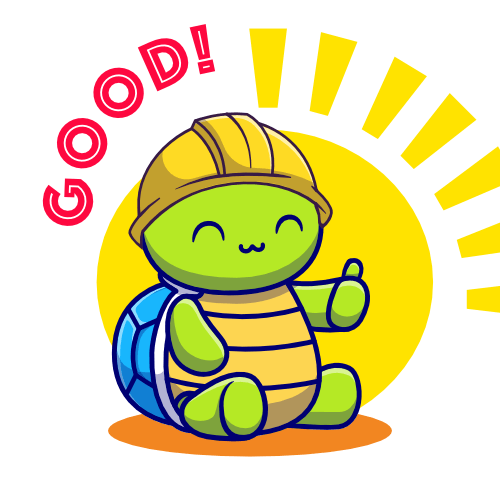
最近は、住宅会社側で「気密測定」を行うところが出てきました。気密測定は「建ててみないとわからない」が故に、ちゃんと施工できるところなら実力を保証する基準としても利用できるからです。
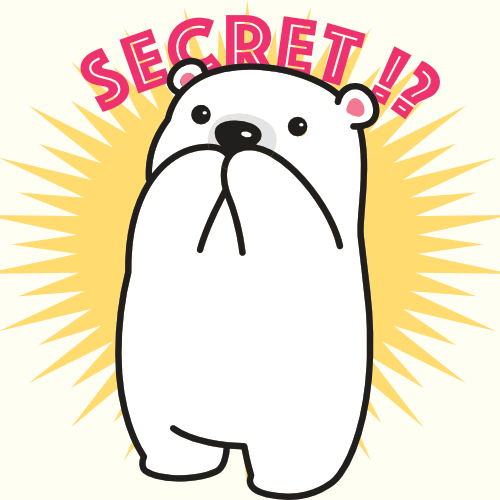
逆にいえば、ハウスメーカーとしては気密測定は保証の範囲外としたいところなんですよね、どれだけやり直しても測定結果が出なければ無駄な仕事になりますから。
ZEH対応
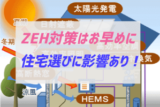
- エネルギー
オール電化かガス併用か - 創エネ方法
太陽光発電、エネファーム - 省エネ方法
エコキュート、エコジョーズ
家の性能の家づくりノート表
| 項目 | 要望 | 備考 |
| 耐震性能 | – | 住宅会社に聞くところ(耐震性能を上げる工夫は何か、具体的な指標は説明されているか) |
| 耐震等級 | 1・2・3 | |
| 制震対応 | 制震ダンパーなど | だいたいプラス50万円くらいでできる工事です。 |
| 免震対応 | 免震装置など | だいたい200万円くらいですがピンキリ |
| 断熱性能 | 省エネ基準に対しての計算値 | 説明義務があるので丁寧な説明ができるかチェック |
| 使用断熱材 | ( )厚み( ) | 使用している断熱材と、厚みを確認する。施行中、吹き付けだったら厚みを測定し、基準に達していなければやり直してもらう。 |
| 気密性 | C値( )建築中の測定検査(する・しない)保証(あり・なし) | 見積もり段階で気密測定をするか、測定した場合、メーカーで保証しているところまで工事をやり直すか。 |
| ZEH対応 | あり(金額: )なし | ZEH対応は結構大変です |
| 省エネ | エコキュートなど | |
| 創エネ | 太陽光発電、エネファーム | 電気を作るシステムが必要かどうか |
好きなデザインは画像貼り付けが楽チン
デザインに関しては、余白にどんどん好きな画像を貼っていきましょう。言葉で伝えるよりずっと楽です。
「〇〇風」とか、言ってる方もよくわかんなくなりますよね。和風モダンとか、プロヴァンス風カントリー調とか、ゴシック様式とか、もう何が何だか。
「外観」と合わせて検索するといいそれっぽい単語一覧

外観を調べる際に役に立ちそうな感じの言葉をまとめてみました。自分が想像している家ってどんな感じのものか、色々検索してみると楽しいですよ!
| 和風 | 古民家 | 和モダン | 旅館 | 再生家屋 | 別荘風 |
| アメリカ | ヴィンテージ | カントリー | 西海岸 | ブルックリン | ニューヨーク |
| イギリス付近 | ブリティッシュ | アイリッシュ | ヴィクトリアン | コートハウス | コッツウォルズ |
| 北欧 | ナチュラル | ノルディック | スウェーデン | ログハウス | カフェ |
| 南欧 | フレンチ | プロバンス | ギリシャ風 | ゴシック | アンティーク |
| リゾート | バリ島 | 地中海 | モルディブ | 南国 | コテージ |
お気に入りの画像を見つけたらとにかく保存して共有する
今の時代は、情報過多にはなりがちですが、夫婦で情報を共有する分には便利な時代になりました。
家づくりノートを作る方法という記事内でも画像共有については触れましたが、LINEなど普段使っているコミュニケーションツールでも簡単に代替できるので、ぜひトライしてみてください。

また、家族で写真や画像を共有する際に便利なアプリに関してはこちらにまとめましたので、好みの方法で「家族が目指す家づくり」のイメージを固めてみてください。
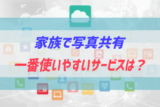
間取りは家づくりノートで一番手間がかかる
間取りは自分で決めようとすると大変です。というか、我々のような素人が失敗する原因です。まずは「生活スタイル」を見つめ直して、ある程度の動線を考慮した方がいいです。
収納計画については、間取り次第なところがあるのですが、「すでに搬入が決まっている大型のもの」については事前に伝えておいた方がいいですよ。
ちなみに、私たちの家は、2階にリビング・キッチンを作ってもらったのに、スリムサイズの冷蔵庫も搬入できませんでした。(計画性がなかった証拠ですね)
間取りの基本項目リスト
- 生活スタイル(寝室を動線から外す、など)
- 家事動線の優先順位(水回りと物干しの距離感、など)
- 家族構成(子供の帰宅動線)
- 階段位置
生活スタイルに置ける家づくりノートテンプレート
| – | チェック項目 | 備考 |
| 生活スタイル | – | 家族構成、職業上の配慮(夜勤など) |
| 仕事 | 帰宅時間、就寝時間の違い | 仕事上の配慮が必要なら(子供が寝てからの帰宅だと帰宅動線から寝室を外す、など) |
| 家族構成 | 子供部屋、2世帯など配慮が必要か | 子供部屋は2つつくるなら将来壁を作る方法も。(小さいうちは利用機会の少ない部屋になるので) |
| 就寝時間の配慮 | – | 夜勤などの時差勤務だと、動線から寝室を外すか昼寝部屋をつくるといい。 |
| 子供の帰宅動線 | 子供部屋の位置 | リビングを通るように、など |
| 趣味 | 大型収納、防音部屋、棚(CD,本などどのサイズが欲しいか) | 防音は超高級品なので、どこまで求めるのかは入念な打ち合わせが必要 |
| 子供の部活、習い事、勉強 | 練習スペースや、リビング勉強なら本棚の位置など確認 | 子供が小さいとわからないけどね |
| ペット | 出入り口にシャワー、部屋 | 熱帯魚とかだと水槽スペースと電源取りも必要 |
| 介護対応 | バリアフリー、廊下幅、手すり、スロープ | 介護保険適応になるので、リフォームの方が安く上がることも |
| 家事動線 | 水回り、洗濯、 | – |
間取りの各部屋のチェック項目
- リビング:吹き抜け、階段位置、広さ
- ダイニング:リビングとキッチンとの距離感
- キッチン:形状 対面、アイランド、壁付、別室
- お風呂:広さ1坪(やや狭い)1.25坪(ほんのり広い)
- 子供部屋:数、後から壁を足す、など
- 寝室:ベッドのサイズなど注意。化粧台や書斎などを隣接するか
- サンルーム:個人的には必須。屋内物干しは天気に左右されず、除湿機設置だけで簡単に乾くのでおすすめ。
部屋と合わせて収納計画も立てよう!
- 収納計画(優先度、間取りと予算)
- すでに決まっている大型収納家具(タンスなど)あれば:サイズ
- 各部屋:クローゼット、押入れサイズ
- シューズクローク
- ウォークインクローゼット
- 納戸
- 外部収納
- 階段下収納
収納に関する記事で読んでおいてほしいもの
収納と間取りについての考えをまとめた記事があります。

収納の関連記事一覧
間取りと収納に関する記事一覧
- スペースを取らない布団の収納術!快適な睡眠環境を手軽に実現する方法
- もう、広い家はいらない? 物置シェアで収納いらず
- 小上がり和室の段差の決め方「床下収納と登りやすさ」
- 新築時の可動棚サイズはカラーボックスを参考にすべし
- 納戸、外部収納、シュークローク、ロフトは不要
- 子供部屋の収納にクローゼットはいらない「ライフサイクルを考慮」
間取りの部屋別家づくりノート項目
| – | チェック項目 | 収納計画 | 備考 |
| リビング | 広さ( )家具(ソファの大きさ: 、テレビ台: ) | 掃除用具、こどものおもちゃ、ニッチに写真飾る、スイッチ隠す、電源位置 | 収納計画は絶対にしておく(リビング収納超大事) |
| ダイニング | 広さ( )ダイニングセット、キッチン側にカウンター | 食事の道具など | 子供をリビングで勉強させる、家事スペース確保なら別にカウンターの設置など |
| キッチン | 広さ( )形状(アイランド、対面、壁付I型) | パントリー(食品庫) | |
| お風呂 | 広さ(1坪、1.25坪、1.5坪、脱衣所、洗面所 | 掃除用具、着替え、バスタオル干し、汚れた洗濯物 | |
| トイレ | 1階( )2階( ) | トイレットペーパー、掃除用具などの収納 | トイレを増やすと掃除場所も増える |
| 寝室 | ベッドサイズ、布団、夫婦同室、別室などの対応 | 布団、来客用布団、シーツ、布団、布団乾燥機 | ベッドにする場合、赤ちゃんをどこに寝かせるか、スペース配慮必要。 |
| サンルーム | (必要・不要)どこで物干しするか | ハンガー、大物を干す道具(布団など)、洗濯機の位置 | どこで物干しするか。洗濯機の位置は要検討。 乾いたものを運ぶより、濡れたものを運ぶ方が大変。 |
| 収納部屋 | シューズクローク、ウォークインクローゼット、納戸、外部収納 | 大型家具、季節家電・家具、子供の作品など | 大きい収納部屋より手の届くところの小さい収納を意識する |
家づくりノートテンプレートのまとめ
記事をお読みいただきありがとうございました。

こう、もっとiPhoneのアプリとかにしてチェックするだけで簡単プリントアウト、みたいな感じにできれば良かったのですが。力及ばず。
最後に、簡単にページ内容をまとめて「家づくりノートはこうしたらいいよ」みたいなことがお伝えできたらいいかな、と思います。
家づくりノートをつくるということ
私の家づくりを始めた、つらかったのは「会社を選ぶとき」です。
「断るのが申し訳ないな」と思ったり、見積もりしてもらった会社に急かされたりして、なんだか感情の揺さぶりが強すぎて一時期「家づくり辞めたい」と思ったくらい、つらい時期でした。
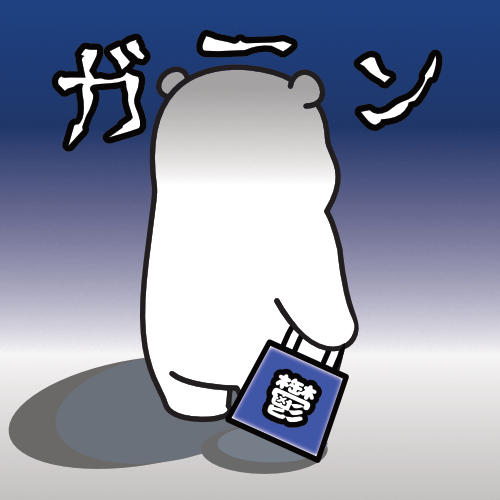
営業だから「みんないい人」に見えるのは当然というか作戦なんだけど、それでもやっぱり断ったりするのはつらい気持ちになるよね。
家づくりノート以上の情報を引き出せる会社でもいい
家づくりノートはあくまでも「各社勢揃いの状態でのたたき台」です。こちらが用意した家づくりノートを活用して、自社のメリットを生かしていろいろな提案をしてくれる会社なんかは「いいなぁ」と感じるところ。
一方で、「この予算じゃできない」で終わるところは少し残念。具体的に「ここは我慢することになるけど、その代わりここはもっと上手くできる」などの代替案をどんどん出して「家づくりを一緒にできる」と感じられるところなんかを選ぶと「家づくりが楽しくなる」と思います。
家づくりノートのまとめ方
家づくりノートの要素に関する情報をまとめておきます。
予算だけは妥協しない
お金をかければいい家が建つ、ということもないのが住宅業界の罠でもあるのですが、資金に余裕があった方が提案のバリエーションが増えるのは事実です。
一番いいのは、「この家はもっと予算出せそうだな」という雰囲気だけ出しておいて、しかし当初の予算を絶対に超えさせないこと。

予算が少ないと、住宅会社としては「切り捨ててもいい客」になってしまうので、対応がガラッと変わることも。予算はありそうな雰囲気を出すのって案外大事。

だけど、予算の不可侵ラインは絶対に作っておく。「頑張ればもうちょっと出せるかも」は契約した後でいいので、計画段階では絶対に当初の予算で収まるようにして、契約までは乗り切りましょう。
まとめ:家づくりノートのテンプレも自作
家づくりノートのテンプレのテンプレみたいなものはネット上にたくさんあるので、自分の使いやすい形に落とし込むことをお勧めします。
大事なポイントは、「何のために家づくりノートを作るか」を見失わないこと。

過去に取材を受けた時に「家族のコミュニケーションツールとして利用していた」とカッコよく答えていましたが、確かに「自分の好み」を相手にしっかり伝えるのって難しいんですよね。

家づくりを勉強すればするほど、「できること」「やらないといけないこと」が増えていくんだけど、整理していかないとパンクしちゃいますからね。行き着く先は、熱量の差で生まれる家族の喧嘩。
まずは、共通言語として、家づくりノートの項目を埋めていく、埋めながら、知らないことがあれば調べてみる。これを家族や住宅会社の担当としっかり共有していく。
家づくりノートのテンプレートで知っておきたいこと
- 家づくりノートは見積もり取ってもらうときに住宅会社に提出する時コピペできるとラク
- 家づくりノートのテンプレが埋められないところは「知らないところ」なのでしっかり調べる
- 住宅会社に相談するのは基礎知識を蓄えてから
家づくりノートに関する記事リスト
家づくりノートを作りたいと考えている方に役立ちそうな記事をまとめておきました。
家づくりノートに関するページ一覧
まずは家づくりノートのテンプレートを見ながら、準備できるといいかな、と思います。





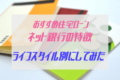

コメント
「間取り 建てる 病院」に関する最新情報です。
獣医の石井さん夫婦は、子供が成長し子供部屋が必要になったため新しい家を建てることにしました。以前に建てた動物病院併用住宅の2階に住んでいたが、夏は暑く冬は寒いというストレスがありました。そのため、高気密高断熱にこだわった地元の工務店で新しい家を建てることにしました。
https://gendai.media/articles/-/123261
「耐震性 崩壊 外観」に関する最新情報です。
この記事は、タワーマンションの耐震性についての診断方法について説明しています。タワーマンションの一階部分が一気に崩壊する事例があり、外観から耐震性を判断することができるのかについて検証しています。記事では、タワーマンションの耐震性は地盤の問題や建物の揺れに対する共振などによって決まると説明されています。また、建物の外観から耐震性を見極める方法や、特に注意が必要な要素についても紹介されています。
https://gendai.media/articles/-/122731
「地震 付近 震度」に関する最新情報です。
佐渡付近で地震が発生し、長岡市で最大震度5弱を記録しました。地震の規模はマグニチュード6.0で、震源地は佐渡の近くでした。この地震による津波の心配はありません。
https://www.niikei.jp/932322/
「卵焼き 材料 作り方」に関する最新情報です。
このウェブサイトは、卵焼きにきなこを使った美味しいレシピの作り方を紹介しています。材料はたった3つで、簡単に作ることができます。きなこを加えることで、一味違った風味が楽しめます。記事では、具体的な作り方やポイントも詳しく解説されています。また、埼玉県秩父市にあるだいずSUNファームの取り組みや、地元の農家との関わりについても触れられています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65838849e4b0fe4ffe320310
「タオル 月間 10」に関する最新情報です。
タオル美術館グループは、「1枚のタオルづくりから10年後の地球を考える」リボーンコットンプロジェクトの強化月間を開催する。これは、10月が「3R推進月間」であることに合わせて、タオルの回収を強化する取り組みである。タオル美術館グループは、リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)の3Rを推進し、循環型社会の形成を目指している。具体的には、全国の直営店舗や百貨店、ショッピングセンターなどにタオル回収ボックスを設置し、タオルの回収キャンペーンを展開する。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000020357.html
「防災 意識 住宅」に関する最新情報です。
パナソニックホームズの調査によると、防災対策において「食料・水の確保」が最も重要視されていることがわかった。しかし、住宅の補強に関する意識は不十分であるという結果も示されている。また、コロナ禍の経験から在宅避難の重要性が高まっているが、住宅の耐震補強や家具・家電の転倒防止器具の設置などについてはまだ十分な取り組みが行われていないことが明らかになった。この調査は、関東大震災から100年が経過する2023年7月に実施されたものである。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vd3d3Lm5pcHBvbi5jb20vamEvamFwYW4tZGF0YS9oMDE3NjEv0gEA?oc=5
「12 12 倒壊 ann」に関する最新情報です。
カナダで巨大な竜巻が発生し、住宅など12棟が倒壊しました。このニュースはテレビ朝日系のANN(アスヒ・ネットワーク・ニュース)でも報じられています。竜巻はカナダの西部で発生し、被害が発生した地域では警戒が呼びかけられています。現地の消防車や救急車が出動し、負傷者も出ていると報じられています。この竜巻の発生は、カナダの建国記念日にあたる日に起きたため、関連する行事や祝賀行事が一時中止になったとのことです。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vbmV3cy55YWhvby5jby5qcC9hcnRpY2xlcy9jNmZhZjUxYzc3MmYzNWQ5MDdiZjIwMTMxZjYwNDI3Yjg2MWQ0NTBm0gEA?oc=5
断熱等性能等級の部分が、かなり間違って書かれてますよ~。修正された方が良いかと思い、おせっかいながらコメントさせていただきます。
「通りすがり」様、コメントいただきありがとうございます。
断熱・気密等の性能に関しては最新の情報を反映させるため下調べが必要だと判断しました。修正まで時間を要すると思います。ご指摘いただきありがとうございました。